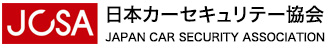盗難車の“通貨”化が進む中、2024年に盗難台数の27.5%を占めたトヨタ・ランドクルーザーが象徴するのは、モビリティが単なる移動手段から高流動性資産へと変貌した現実だ。背景には新興国の需要爆発、部品価値の上昇、そして闇経済による“グローバル裏物流”の構築がある。
28%集中の異常事態
高価格帯のスポーツタイプ多目的車(SUV)の代表格であるトヨタ・ランドクルーザーが、再び車両盗難件数のトップに立った。
日本損害保険協会が2025年3月3日に発表した「第26回自動車盗難事故実態調査結果」によると、2024年に発生した車両本体盗難のうち、実に「27.5%」がランドクルーザーだった。これは
「4台に1台以上がランドクルーザー」
という衝撃的な数字である。なぜここまで特定車種に盗難が集中するのか。その背後にある経済合理性を掘り下げていくと、自動車を取り巻く
・グローバルな需給ギャップ
・部品供給網のひずみ
・デジタル制御時代の逆説
が見えてくる。
“通貨”としてのランドクルーザー
ランドクルーザーは単なる高級車ではない。それは、国境を越えた価値交換の“通貨”であり、動く資産でもある。
北米や中東、アフリカ諸国において、頑健な車体と悪路走破性を備えるこのモデルは、軍用・建設・治安維持など多目的に利用されており、インフラ整備が未成熟な地域では事実上のインフラとすらいえる存在だ。
とくに新興国では、新車の納期が1年以上かかるケースも珍しくなく、正規ルートでの調達が困難な地域ほど中古車への依存度が高まる。その結果、日本国内で数年落ちのランドクルーザーが、中古であるにもかかわらず新車価格を上回る価値で取引される現象も発生している。
現地通貨との為替差や関税構造も加わり、実質的にランドクルーザーは「ドル建て資産」に近い流通性を持つ。
密輸部品が動かす裏経済圏
当然ながら、こうした国際的な需給の歪みに目をつけたのが、犯罪組織や非正規ディーラーによる闇経済のプレイヤーたちである。彼らはランドクルーザーを単なる車両としてではなく、部品単位で分解・再統合可能な金融商品として捉えている。
実際、国内で盗難された車両は、迅速に解体され、
・エンジン
・サスペンション
・ECU(電子制御ユニット)
など高価値部品に分けられたうえで海外へ輸送される。完成車としての輸出ではなく部品として持ち出すことで、関税や検問といった法規制をすり抜けやすくなる。さらに、現地で再度組み立てられたり、別車種への移植に利用されたりと、違法ながらも効率的なリユース市場が成立している。
このようにして成立するのが、正式なサプライチェーンとは異なる
「もうひとつのモビリティ流通圏」
である。そこには、トレーサビリティも保証も存在しない。だが皮肉なことに、この闇のサプライチェーンが一部地域におけるモビリティ需要を支えているという構図も否定できない。
ランドクルーザーの盗難多発は、単なる治安の問題ではない。グローバル市場におけるモビリティの流通と価値形成に関する構造的課題なのである。
ハイテク化が誘因となる皮肉な構造
盗難対策の高度化は、皮肉なことに窃盗団にとっての標的選定ガイドラインになっている。
新型ランドクルーザーには、衝突回避支援や車線逸脱警報といったアクティブセーフティ機能、さらに通信ネットワークと連動する高度なコネクティビティシステムが標準搭載されている。これらのECUやカメラ、LiDAR、センサー類は、車両本体とは切り離しても非常に高い転売価値を持ち、「車両一台」という単位以上の分解的価値を生み出している。
つまり、ランドクルーザーは単なる車両ではなく、高性能な電子デバイスの集合体として、パーツ単位での価値再分配が可能な
「移動型パーツ倉庫」
のような存在となっている。犯罪組織にとっては、一台の盗難車から最大限の経済的リターンを得るテクノロジー資源の収穫対象として見なされているのである。
その結果として、1件あたりの支払保険金は上昇傾向にあり、損保業界によれば2024年は約20%増加というデータも出ている。これは、単に高額車両の盗難が増えたというだけでなく、搭載されたテクノロジーの価値が保険支払いのコスト構造にまで影響を与え始めている証左である。
国内再販困難化が促す密輸加速
また、盗難車両を日本国内で再登録・再販するのは現実的には困難だ。
・車台番号の管理
・登録履歴のデジタル化
によって、トレーサビリティは年々強化されており、国内での違法流通リスクは高い。そのため、盗難車両の多くは港湾部へと運ばれ、アジア・中東・アフリカへと転送されていく構造が出来上がっている。
ここに物流と地理的要因が重なり合う。たとえば2024年、埼玉県が12年ぶりに「自動車盗難件数ワースト3」にランクインした背景には、広大な郊外型駐車場が多数存在し、さらに高速道路と港湾施設へのアクセスが極めて良好であるという、
犯罪側にとってのオペレーション効率のよさがある。窃盗団にとって、ランドクルーザーのような高価格・高性能車をスムーズに収穫・輸送できるロケーションは、極めて戦略的な拠点となるのだ。
このように、高度な盗難対策や電子化が進めば進むほど、その裏をかくように犯罪側もシステムとして進化し、グローバルなロジスティクスに組み込まれていく。ランドクルーザーはその象徴的存在であり、日本のモビリティ産業における裏の流通経済圏を浮き彫りにしている。
グローバル財としてのクルマ
ランドクルーザーが犯罪者にとって魅力的なターゲットとなる最大の理由は、
・換金性の高さ
・耐用性
・解体しても価値が落ちにくい構造
という三拍子が揃っている点にある。これは裏を返せば、ランドクルーザーがいかに経済財として優秀かを物語っている。単なる移動手段を超え、
・どの国でも売れる
・どんな環境でも動く
・どの部位も使える
という特性は、もはやグローバルな金融商品のような性格を帯びているのだ。
こうした価値は、ある意味で製品としての完成度の高さを証明する皮肉な勲章である。ランドクルーザーの品質が高ければ高いほど、裏市場での再流通リスクも比例して高まるという構図は、モビリティが消費財から資産へと変貌を遂げた現代ならではの現象である。
所有コスト化する防犯
しかしその一方で、盗難リスクの増大は、所有者に新たなコスト構造を強いる。防犯アラームやGPS追跡装置などの後付け機器の導入に加え、セキュリティガレージや車両保険のオプション強化といった、所有にともなう間接コストが無視できないレベルになってきている。また、2024年以降の保険業界においても、ランドクルーザーのような高リスク車両に対する保険料の上昇傾向が指摘されており、
「持つだけで割高」
という事態が進行している。さらに重要なのは、ランドクルーザーを所有するという行為自体が、単なる車を持つことではなくなってきているという点である。それは高価格かつ高機能な移動資産を、常に
「公共空間で晒す」
という意味を持つ。車両自体の価値がこれだけ高まると、所有とは保有であると同時に、守るというアクティブな行為にならざるを得ない。これはユーザーの心理的負担や日常的な運用スタイルにも大きな変化を及ぼしている。
今後も同様の高付加価値モビリティが市場に投入されることは間違いなく、そのたびに安全に所有するとはどういうことかという問いが繰り返されることになる。もはや、メーカーによる盗難対策だけでなく、行政、保険業界、ユーザーが一体となって、モビリティを取り巻く安全性の再定義に取り組む必要がある時代に突入しているといえるだろう。
出典元:Merkmal(メルクマール)